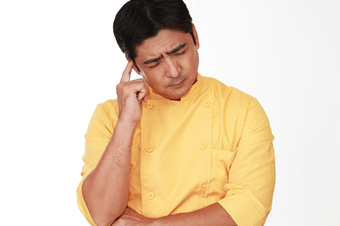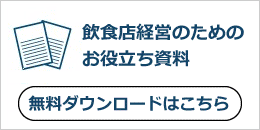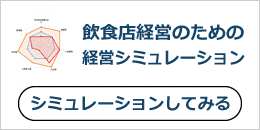- 利益アップ・コスト削減
飲食店の原価計算例を紹介!

飲食店における原価計算は、食材の仕入れが複数の料理に紐づき、また歩留まりや廃棄の考慮が必要なこともあって難しい部分もあります。そこで、このコラムでは 簡便な計算例を紹介します。ぜひ参考にしていただき、お店の食材の性質やメニュー数などを踏まえ、工夫して取り組んでみていただければ幸いです。
本コラムの目次
財務会計(帳簿付け)を利用したアプローチ
個人事業として営んでいる飲食店では、確定申告のために帳簿付けを行なっていると思います。その帳簿付けについて確定申告期にまとめてやっている場合には、
売上と仕入についてだけでも毎日会計ソフトに入力するようにすれば、自動的に1日単位の粗利益を計算させることができます。この推移を意識することで、飲食店経営について売上だけではなく粗利ベースで管理することができます。
ただ、今日の食材仕入れは、当日の売上分だけでなく、明日以降の料理に使用される場合もあると思います。在庫の棚卸についても、帳簿付けとして反映させるのは、年末の決算整理仕訳のみという場合も多いと思います。
したがって、使用する食材が限られており、数日以内に料理で使うか、余ってしまった分は廃棄しているというお店の場合は、帳簿付けを元にアプローチするだけでも有効な方法となりえます。一方、
食材をある程度ストックし、メニューも多いお店では、財務会計によって日次の食材原価と粗利を管理する方法では、十分とは言えないかもしれません。
簿記の学習の中にも製造原価計算という内容があり、試験の分野の一つにもなっています。ただ、それを通じて学ぶ対象は「工業簿記」と言われているように、基本的には工業製品に適した考え方となります。
例えば製造原価について「製造直接費」「製造間接費」に分類する考え方があって、後者は製品の出来高数量や金額の割合を元に、各製品の製造原価に配賦(按分)するという考え方をします。
飲食店においては調理のためのガス代や水道代が「製造間接費」のイメージに近いのですが、ガス代について、実際には料理毎に火力も調理時間も違うと思いますので、馴染まない感じがします。水も料理毎に使用量が違いますし調理以外でも使用します。それらを配賦として精緻厳密に定義していくのは、現実的でないように思われます。
レシピによるメニュー毎の原価の可視化
そこで飲食店では、自分のお店の業態や営業の実態に応じて、独自に原価管理を行なうことが現実的です。一般的には、 メニュー毎のレシピから食材使用量を算出し、メニュー毎の原価を可視化するというアプローチをしていくことになります。 大手飲食チェーンは、セントラルキッチンによる一括生産、レトルト技術などによる食材保存の長期化、厳密なポーションの規定などを組み合わせることで、このような管理を精緻に行っています。たとえば、均一なライスの盛り付けを思い浮かべてみてください。これによりサービスの均一化はもちろん、その一杯によって生じる実際の原価と計算上の原価を一致させているのです。
個人で営まれている飲食店において取り組める範囲は限界がありますが、可能な限り 食材利用の規定量をレシピにしっかりと定め、それを守ることは意識してください。そうしないと、計算上の原価と、実際の食材費が一致しなくなってしまい、原価計算をしている意味がなくなってしまいます。
具体的な計算例
それでは、上記の考え方で、具体的な計算イメージを例示してみたいと思います。チキンカレーとオムライスをどちらも600円で提供している飲食店があったと仮定して、その計算イメージを示します(※ご理解いただきやすいように、簡略化しています)
食材毎の原価リスト
| 食材 | 仕入単価(単位:円) | 内容量 | 単位 |
|---|---|---|---|
| カレー粉 | 3,000 | 3,000 | g |
| 玉ねぎ | 1,000 | 10,000 | g |
| ニンジン | 2,000 | 10,000 | g |
| ライス | 2,500 | 10,000 | g |
| 鶏肉 | 1,300 | 2,000 | g |
| 卵 | 2,000 | 100 | 個 |
| バター | 3,000 | 1,000 | g |
| ケチャップ | 1,000 | 3,000 | g |
メニュー毎のレシピを元にした原価表
| 料理 | 食材 | 使用量 | 単位 | 原価(単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| チキンカレー | カレー粉 | 30 | g | 30 |
| バター | 10 | g | 30 | |
| 玉ねぎ | 50 | g | 5 | |
| ニンジン | 50 | g | 10 | |
| 鶏肉 | 100 | g | 65 | |
| ライス | 200 | g | 50 | |
| 計 | 190 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売価 | 600円 |
| 原価 | 190円 |
| 粗利 | 410円 |
| 原価率 | 31.7% |
| 粗利率 | 68.3% |
| 料理 | 食材 | 使用量 | 単位 | 原価(単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| オムライス | ケチャップ | 60 | g | 20 |
| バター | 10 | g | 30 | |
| 玉ねぎ | 30 | g | 3 | |
| ニンジン | 30 | g | 3 | |
| 鶏肉 | 60 | g | 39 | |
| 卵 | 3 | 個 | 60 | |
| ライス | 250 | g | 63 | |
| 計 | 221 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売価 | 600円 |
| 原価 | 221円 |
| 粗利 | 380円 |
| 原価率 | 36.8% |
| 粗利率 | 63.3% |
この計算例のチキンカレーのレシピでは、カレー粉を30g使用することになっています。
食材毎の原価のリストに照らすと、カレー粉は3,000gを3,000円で仕入れているため、30g使用すると30円の原価がかかっている計算になります。
このような考え方で、チキンカレーを
調理するために使用する食材毎の原価を計算し、それをすべて合算すると、チキンカレーの原価を求めることができます。
なお、この計算例においては、
各食材のうち歩留まりが想定される食材の使用量は調理ロスも織り込んだ使用量としています。例えば玉ねぎの使用量50gのなかには、実際に利用する可食部分45g(歩留まり率90%想定)に、皮の部分5gを含んで計算することで、調理時点の廃棄についても原価に織り込むようにしています。
また、 長期保存で傷んでしまった等の調理外の廃棄は、別途記録します。例えばある1週間に単価600円のチキンカレーとオムライスがそれぞれ100皿出ていて、途中古くなった卵を20個廃棄した場合には、次のようになります。
| 週間売上 | 数量 | 売上単価 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンカレー | 100 | 600円 | 60,000円 | 190円 | 19,000円 | 41,000円 |
| オムライス | 100 | 600円 | 60,000円 | 221円 | 22,050円 | 37,950円 |
| 計 | 120,000円 | 73,617円 | ||||
| 週間中の廃棄 | 数量 | 売上単価 | 売上 | 原価単価 | 原価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別途廃棄:卵 | 20 | 20円 | 400円 |
| 粗利 | 78,550円 |
|---|
このようにすることで、料理の出数に伴った売上と原価に加え、 廃棄の状況も織り込んだ粗利管理を行なうことができます。
財務会計(帳簿付け)との一致精度を高める
さて、このような形でメニューの出数を元とした原価管理を行なう一方で、帳簿付け(財務会計側)での食材仕入れの仕訳は、実際の仕入金額で別途並行して処理することになります。 事情から、例えば前者と後者の一か月の集計を比較した場合、厳密に一致することはまずないと思います。ただ、この 誤差が大きすぎる場合は、別途前者の管理を行なう意味がなくなってしまうので、 運用を調整して管理精度を高める必要があります。
例えば取り扱っている食材が価格変動の激しい生鮮食品でその価格が急騰した場合、原価管理に対して帳簿上の仕入額が大きく、かつそちらの方が実態に近いということになります。この場合には食材毎の原価のリストにおける仕入単価の見直し頻度を高めるなどにより、財務会計との一致精度を高める必要があります。
あるいは、鶏肉について原価管理に対して帳簿上の仕入が多く、調べたら想定したより皮筋や脂身部分の取り除きが大きかったという場合には、歩留まりを含めた使用量の基準を見直すなどの調整が必要かもしれません。
このようにして、原価管理と帳簿付け(財務会計側)の一致精度を調整します。
粗利ミックスを改善する
原価計算が帳簿付け(財務会計)と相当程度一致するようになってきたら、原価計算を元に有益な検討をいろいろと行なえます。料理ごとに食材やその調達先、使用量を見直すなどによりメニュー毎の粗利を高めるなどといったことはもちろんですが、ぜひ 粗利ミックスについても検討してみてください。
粗利ミックスとは、粗利益率の高い商品と低い商品をうまく組み合わせた商品構成により、最終的に一定額の粗利益を確保する手法です。
先ほどの例では、一律一皿600円で粗利率の高いチキンカレーと粗利率の低いオムライスを販売していました。食材の高騰などの影響で価格改定を検討する場合に、一律の値上げではなく、チキンカレーを+50円、オムライスを+100円値上げし、お客様の来店数は値上げ前の1割減程度に留めつつ、出数については粗利率の高いチキンカレーの構成比を増やすことができた場合には、次のような計算になります。
価格改定前
| メニュー | 数量 | 売上単価 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンカレー | 100 | 600円 | 60,000円 | 190円 | 19,000円 | 41,000円 |
| オムライス | 100 | 600円 | 60,000円 | 221円 | 22,050円 | 37,950円 |
| 計 | 200 | 120,000円 | 78,950円 |
価格改定後
| メニュー | 数量 | 売上単価 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンカレー | 120 | 650円 | 78,000円 | 190円 | 22,800円 | 55,200円 |
| オムライス | 60 | 700円 | 42,000円 | 221円 | 13,230円 | 28,770円 |
| 計 | 180 | 120,000円 | 83,970円 |
売上予測の精度も高めよう
原価計算によりメニュー毎の粗利は確保されることになりますが、原価計算以外の部分で、
売上予測の精度を高める必要もあります。メニュー毎の売上数量の予測から必要となる食材仕入れを行なうため、例えば予測した数量に対して実際の数量が下回ると、調理外の食材廃棄ロスによってお店全体の粗利が低下してしまうためです。
売上予測については、日々のメニュー毎の出数実績を元に、時々の天気と気温、周辺におけるイベント開催、固定客の来店サイクルなど様々なファクターを加味して予測精度を高めていく必要があります。
そのためのツールとして、さまざまな集計を自動的に行ってくれるタブレットレジは非常に有効といえるでしょう。このサイトを運営しておりますカシオ計算機でもタブレットレジ「EZネットレジ」を提供していますので、よろしければ導入を検討なさってください。